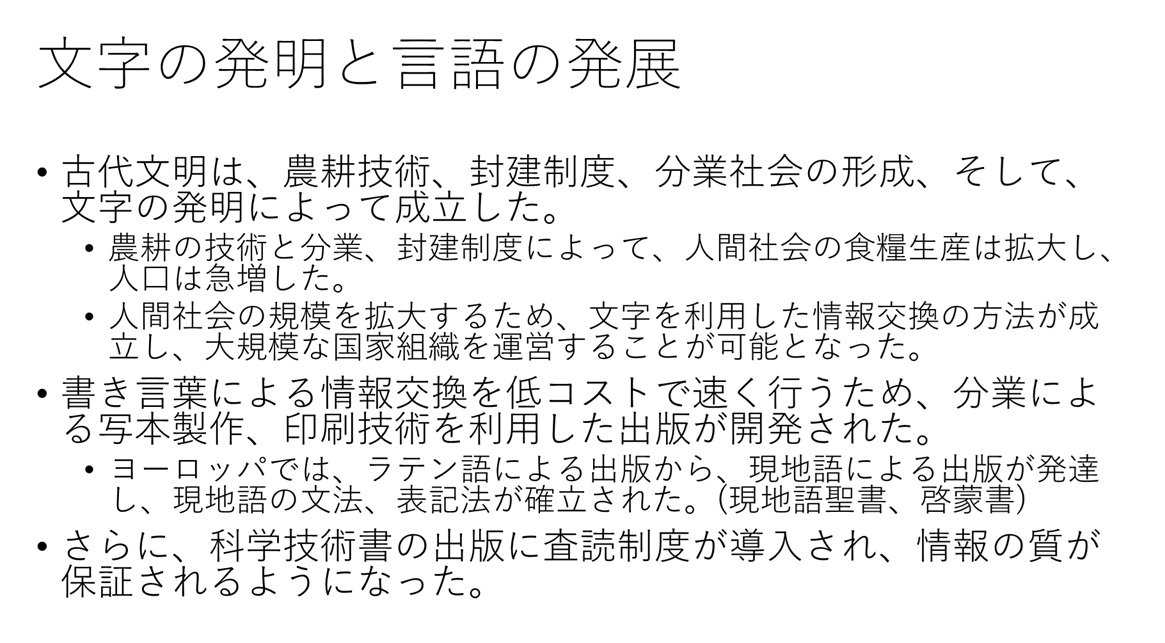言葉と社会 〜 合意の形成
提供: 有限会社 工房 知の匠
文責: 技術顧問 大場 充
更新: 2025年8月29日
人間が集団で生活するようになると、ホモ・サピエンスもネアンデルタール人も、社会を形成するようになりました。その人間が作る社会では、人間相互間での意思疎通を図るため、話し言葉が発達しました。
ホモ・サピエンスが農耕の技術を確立し、封建的な身分制度の社会を形成し始める前、ネアンデルタール人もホモ・サピエンスも、音声を使った言葉による意思疎通の方法を、すでに利用していたようです。もちろん、人類以外の他の動物も、鳴き声などを使った、簡単な意思疎通の方法は使っていました。人類は、その特質でもある長い喉を使って、声帯をうまく動かし、多様な音声を発生するやり方を学び、その多様な発声を活用した、複雑な意思疎通の方法を獲得しました。

図9. 言語と社会
特に、ホモ・サピエンスの場合、約6万5千年前、現在のインドネシアにある「トバ火山」の大噴火で発生した地球の寒冷化の影響で、絶滅の危機に直面し、互いに協力して生きなければならないことを学んだとされています。それは、互いに争って、自分が必要としているものを獲得するのではなく、互いに助け合い、物を分かち合って、種としての人口を増やすことを優先することでした。その相互の助け合いを円滑に行うため、個体同士の相互の意思疎通を行うことが必要でした。それを助けたのが、言葉を使った、相互の意思疎通だったのです。
集団内における意思疎通は、集団の規模が小さければ、比較的、簡単です。そのため、複雑な表現、つまり複雑な意味のやり取りは、必要がなくなります。しかし、集団の規模が一定数を超えると、集団内部での合意の形成が難しくなります。そのような状況でも、集団内での合意を作り上げ、まとめられた合意に従って、一つの集団として、一団となって行動を起こすことが、集団としての社会の存続の可能性を高めることができます。この集団の内部での合意の形成のため、個人の間での意思疎通を図り、意見の一致を探し求めることが重要になります。それを可能にしたのが、豊富な語彙を使った、言葉によるコミュニケーションでした。
初期の言葉によるコミュニケーションでは、単に言葉として音声で表現されたものだけではなく、そのコミュニケーションの場にいた人々の間で交換された、音以外の動作などによる表現も利用されていたはずです。しかし、集団の規模がさらに大きくなると、コミュニケーションが行われる場に集まることができる人々の数にも限界があり、集団のメンバーの中には、合意を形成するための議論の場に参加できない人々も出ます。この場合、議論の場に参加した人々から、言葉による説明を聞き、その合意の内容を知るようになります。このためには、言語による説明のための表現も、時制の明示、仮定や意志の明示など、より複雑になりました。
このような言葉の発展過程を経て、ホモ・サピエンスの使う言語は、ネアンデルタール人が使っていた言葉よりも、複雑な内容を説明できるようになっていたと考えられます。ホモ・サピエンスによる狩猟の道具の進歩を見ると、ネアンデルタール人が使っていた狩猟の道具に比較して、同じ期間に改良された道具の進歩が著しかったことが、遺跡から発掘された道具の比較から分かりました。また、集団の規模についても、ネアンデルタール人の場合、10名程度から20名程度の家族を中心とした集団であったのに対し、ホモ・サピエンスでは、大規模な集団では、200名を超えていた例が発見されています。そのような集団では、単一家族ではなく、様々な人々が、集団で生活していたと考えられています。そのため、言語による意思疎通のための話し言葉も、より進歩したものに変化したと考えられます。
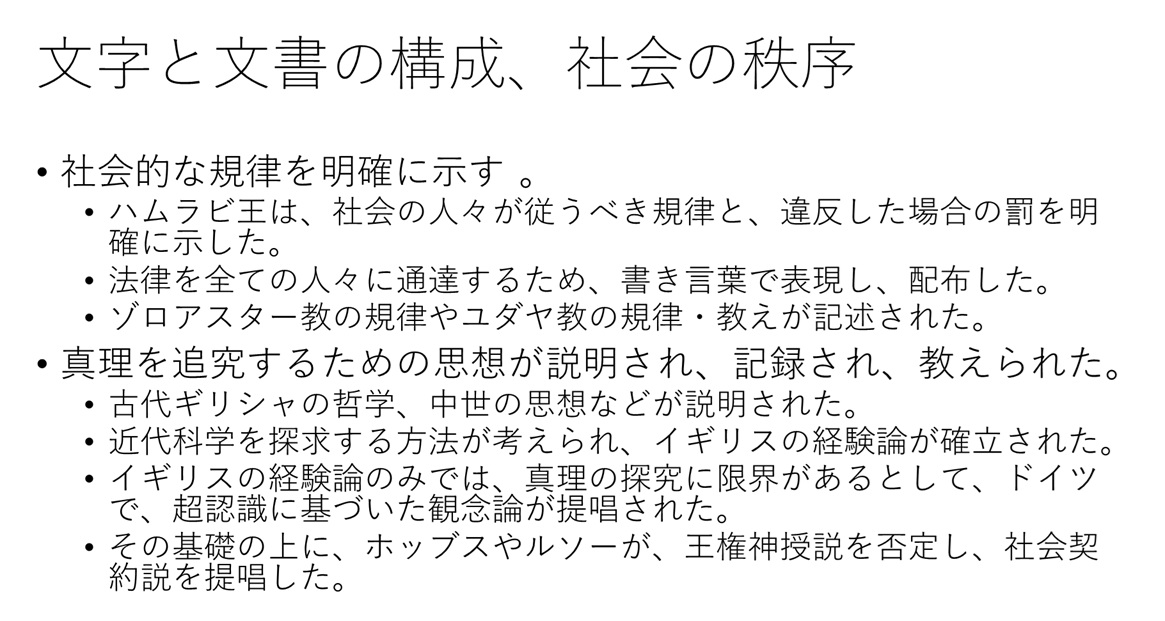
図10. 文と社会規範
15世紀のイギリスの思想家、フランシス・ベーコンは、人類の知識の獲得に、従来の主流であった「演繹法」よりも、「帰納法」が重要であることを主張し、人間相互間での共通の認識を確立することが重要であることを強調しました。この考え方が、中世の思想家、オッカムの唯名論とともに、複数の人間による事象の確認に基づいた、「客観的な認識」を重視したイギリス経験論の基礎になったと言われています。さらに、17世紀になると、政治哲学の分野で、ジョン・ロックやホッブスが出現し、民主主義の根幹をなす思想や、それまでの王権神授説に対立する「社会契約論」が提唱されるようになります。
ホッブスは、国民が国王の統治を受け入れるのは、「国民の個人個人が、個別にそれぞれの権利を主張して、個人的な争いを行うことは、社会的に効率が悪く、王権に、国民の統治を委託することの方が、合理的である」からであると言う説を、主張しました。それは、国民と統治者である国王との間に、暗に、社会的な契約が成立していると考えられることを意味しています。ロックは、国民の自由な権利は、基本的には、統治者である国王でも、犯すことができないものであると、主張しました。それらの権利には、国民が獲得した私有財産の所有に関する権利、個々の国民が信じている宗教の選択についての自由に関する権利、さらに、個々の国民の生命は国王だとしても、勝手に犯してはならないとする、「個人の権利」が認められるべきであるとしました。このホッブスやロックの考え方は、統治者としてのイギリス国王と、国民との間における社会契約上の関係を整理したものであると言えます。
さらに、18世紀の中頃、フランスの思想家、ルソーが「社会契約論」を発表しました。この書物は、ホッブスのリバイアサンと同じように、それまでの国王による国家の統治に対する理論的根拠を与えていた「王権神授説」に対抗して、社会と国民との間には、暗に人民の社会的権利に関する契約が成り立っていると主張していました。このため、王権神授説を支持していたフランス革命以前の社会的支配層であった貴族や宗教関係者からは、反論が提示されていました。近代以降の民主主義社会においては、このルソーの社会契約論は、ロックの「民主主義の原則」と同じように、「国民国家」の法的根拠の基礎を与える枠組みとなりました。