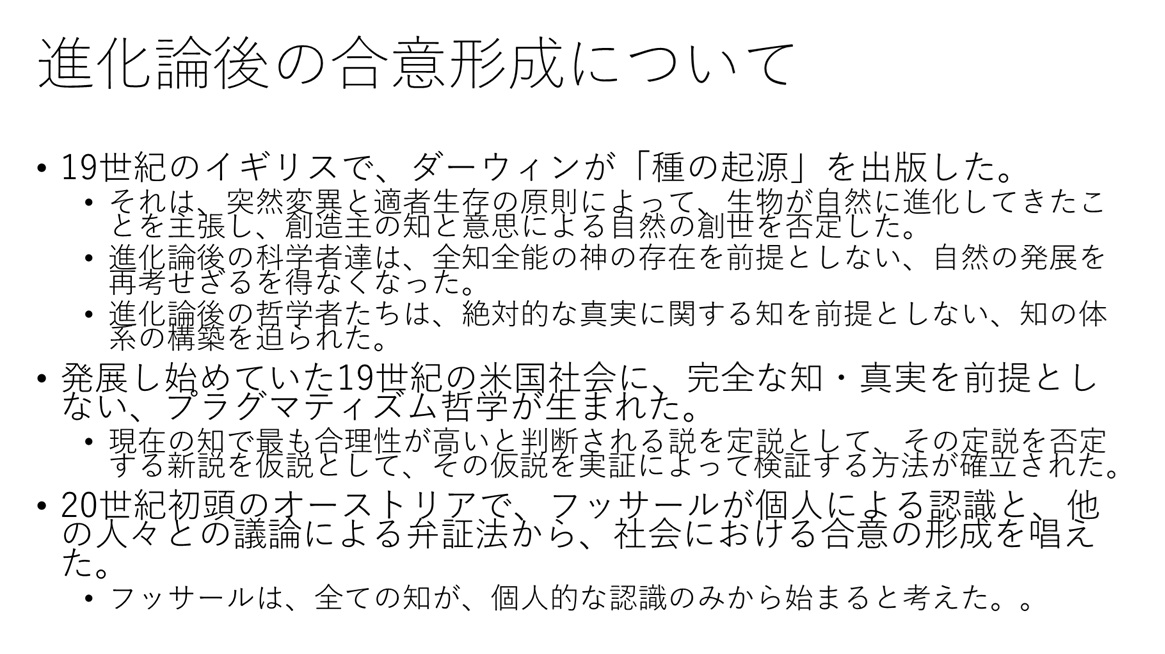認識と合意形成 〜 デカルトからフッサール
提供: 有限会社 工房 知の匠
文責: 技術顧問 大場 充
更新: 2025年8月29日
人間同士が言葉を使って意思疎通を図るようになると、話し手個人の思いや認識を話しているのか、客観的な事実を話しているのかの判別が問題になりました。哲学者のデカルトは、個人的な認識を出発点であるとしても、人々が共通に認識できる、客観的な知に到達できることを主張しました。
ベーコンが17世紀に経験論の基礎となった「帰納法」を提唱し、諸科学における実験による検証を重視する方法が確立されました。これは、人間が認識した事象に基づいて、その事象を生じさせた原因について考え、その主たる原因と考えられる物事を突き止めて仮説とし、この因果関係(仮説)を限定された条件の中で再現し、再現できれば、その仮説は「客観的に正しいと言える」とする考え方です。それ以前、16世紀末にフランスに生まれた思想家デカルトは、人間の知が、万能な神の力で与えられた「天地創造の結果」とするのではなく、人間の理性による思考によって、合理性な考察を積み重ねて獲得された共通の認識であると主張しました。デカルトは、人間の思考を振り返って、その思考が単なる個人の主観(つまり、偏見)のみによって組み立てられているのではなく、思考の細部についても懐疑的な視点で見直すことによって、「単なる主観的な認識のみによって得られたものであるとは言えず、その事実を歴史的に多くの人々が客観的に認識しているので、その正しさは否定できない」と、突き詰めることができました。デカルトが「方法序説」に述べた「われ思う、ゆえに我あり」と訳されたフランス語文の表明は、『私の主観は、単なる「私が、そうと信じている」と言う、私の信念があるだけではなく、「私が、現実に存在する主体であり」、「その考える主体は、客観的に存在している」はずである』と言う証明であると、主張しました。
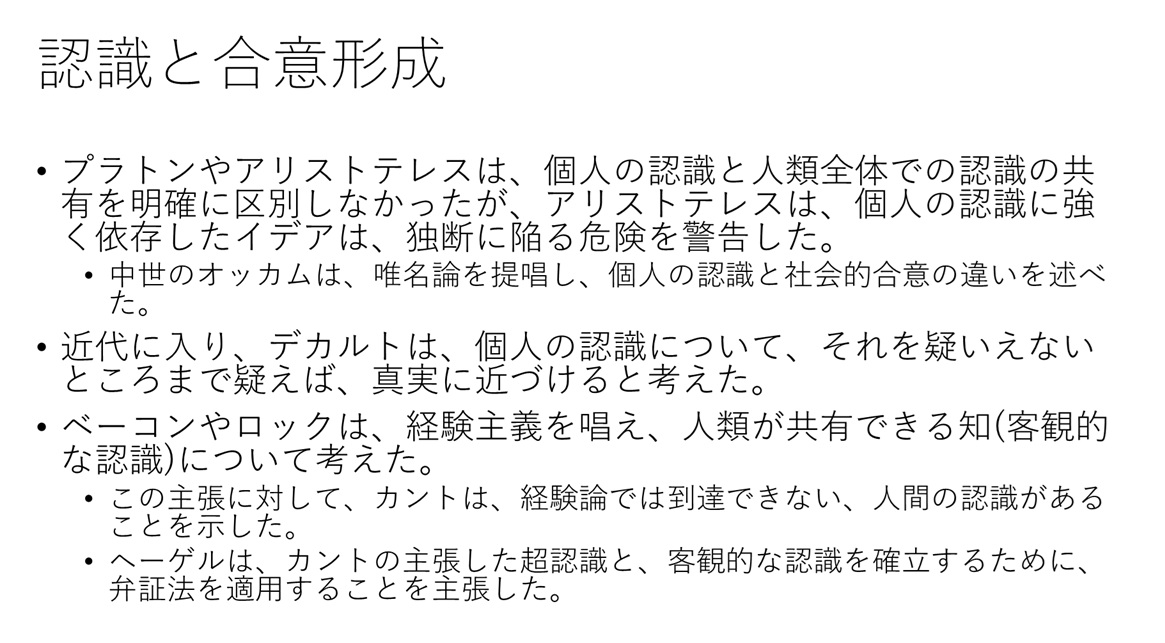
図11. 認識と合意形成
このデカルトの後にも、現象の観測者である主体が、主観的な認識にもとづいて、観察した現象が、その個々の独立した主体以外の人々でも、独立して、客観的に観測することが可能な現象であることを主張するために、哲学者達による、主観と客観の「すり合わせ」ができることを示そうとする努力は試みられてきました。上述した、17世のイギリスで、ベーコンが帰納法と実験によって、客観的な事実として、ある現象を確認できるとしました。これが、イギリスの経験論の基礎となり、産業革命期以後の科学の進歩に大きく寄与しました。それは、中世のオッカムが、アキュナスの実在論による「神の存在証明」は、『神の概念』の存在は証明していても、「神と言う『実体』が、客観的に存在している証明にはならない」、とした唯名論の主張と似ています。観察主体だけでない、独立した第三者の客観的な観察を取り込むことで、主観と客観の「すり合わせ」による、合意の形成を目指しました。
その後、19世紀のドイツの哲学者、カントは、人間の「先験的な知識」の概念を応用して、多くの人間が、直感的に認識できる存在の客観性を主張する立場を取り、イギリスの経験論に対する反論を試みました。これは、『現実に学ぶことができる経験からでは、「無限な広がりを持つ空間や、永遠に続く時間」は、理解できない』とする主張から、人間には、「経験によらずに獲得できる知がある」と、考えました。この「経験によらずに獲得できる知」を、カントは、「先験的な」知と名づけました。このカントの主張の後、主観的な「事象の認識」と、人類による客観的な認識を「すり合わせ」る試みは、継続されています。その一つに、19世紀末のアメリカ合衆国で生まれたプラグマティズム哲学があります。また、それと同じ時代に、ドイツのフッサールが提唱した「現象学」も、主観的な認識と、客観的な認識の「すり合わせ」を行おうとした、試みでした。
プラグマティズム哲学では、『人間には本当の真実を認識する能力はなく、ただ経験した現実を、単なる「個々の現象」として「あるがまま」に認識する能力しかない』と考えます。それは、イギリスの生物学者、チャールス・ダーウィンが、その著書、「種の起源」で主張した、『生物は、突然変異と、その変異が生息環境に適しているかどうかで、適している変異は生き残り、他は絶滅する」とする原則に従って、進化してきた』とする説が暗示する、人間の知は、『絶対的なものではなく、その時代に真理であると信じられているだけのものである』とする、無神論の主張でした。その人間の認識についての制約の中で、現実に対する認識を、より真実に迫る認識に近づけるためには、現在の知識を改良して、より多くの人が共有できる普遍的な真実に近づいていると考えられる知識にしようとします。この思想が、20世紀の科学技術の進歩を支えた、最も新しい哲学です。
これに対して、19世紀オーストリアの哲学者、フッサールは、『人間の認識は、その主体である存在の主観的な認識でしかない』、と考えました。その主観的な認識を、他の主体との意見の交換を通じて、その主観的な認識の問題点を認識し、他者の意見を取り入れながら、抽象化の方法を工夫して、プラトンのイデアのような、より一般性の高い認識(概念)に変えてゆくことで、よい多数の人々と共有できる認識に近づけるべきである、と考えました。ここでは、ヘーゲルが主張した、古典的な方法である「弁証法」を用いて、個人の主観的な認識に基づく理解と、それとは対極的な主観的な認識との2者を対立させ、その相互間の違いを明確にして、その対立する2つの認識の長所・短所を見比べ、この対立する2つの認識の違いを「すりあわせ」て、新しい認識を作り出すべきだとする考えです。プラグマティズム哲学の方法は、このフッサールの方法よりも、「手続き」が明快ですが、その意味するところは、似ています。