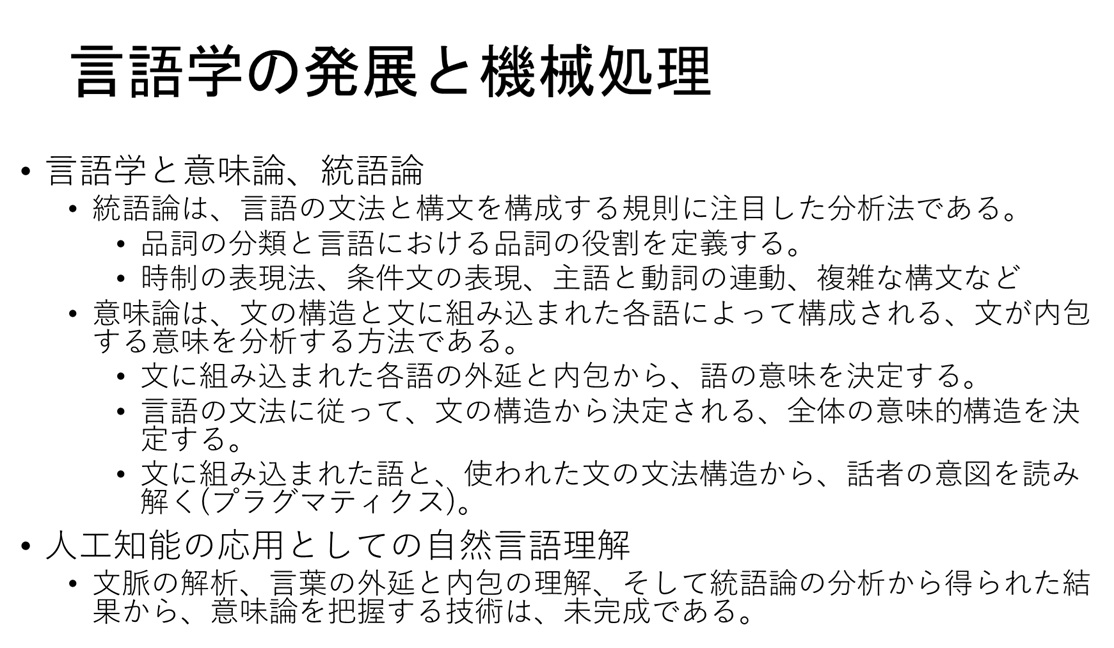機械学習と意味論の解析
提供: 有限会社 工房 知の匠
文責: 技術顧問 大場 充
更新: 2025年8月26日
コンピュータが発達し、人間社会に普及し始めると、人間同士の意思疎通のために、コンピュータを利用して、情報交換を安く、効率的に行うやり方が、広まりました。その代表的な例が、インターネットと、それを利用した、ソーシャル・ネットワーク・サービスです。この外形的な技術の進歩だけでなく、人工知能技術を利用した、話し手の意図した意味の把握を目的とした技術の研究も進みつつあります。
人類の社会で、人間活動の様々な場面において、コンピュータの利用が一般的になり、特に、スマートフォンの開発と普及によって、人々は、いつでも、どこでも、他の人々とつながり、情報や意見の交換を、誰とでもできるようになりました。さらに、インターネット上のソーシャル・ネットワーク・サービスの普及が進み、人々は、いつでも、どこにいても、誰とでも、インターネットを経由して他人とつながり、意見や感想を、見ず知らずの人々とでも、交換し、共有することができるようになりました。
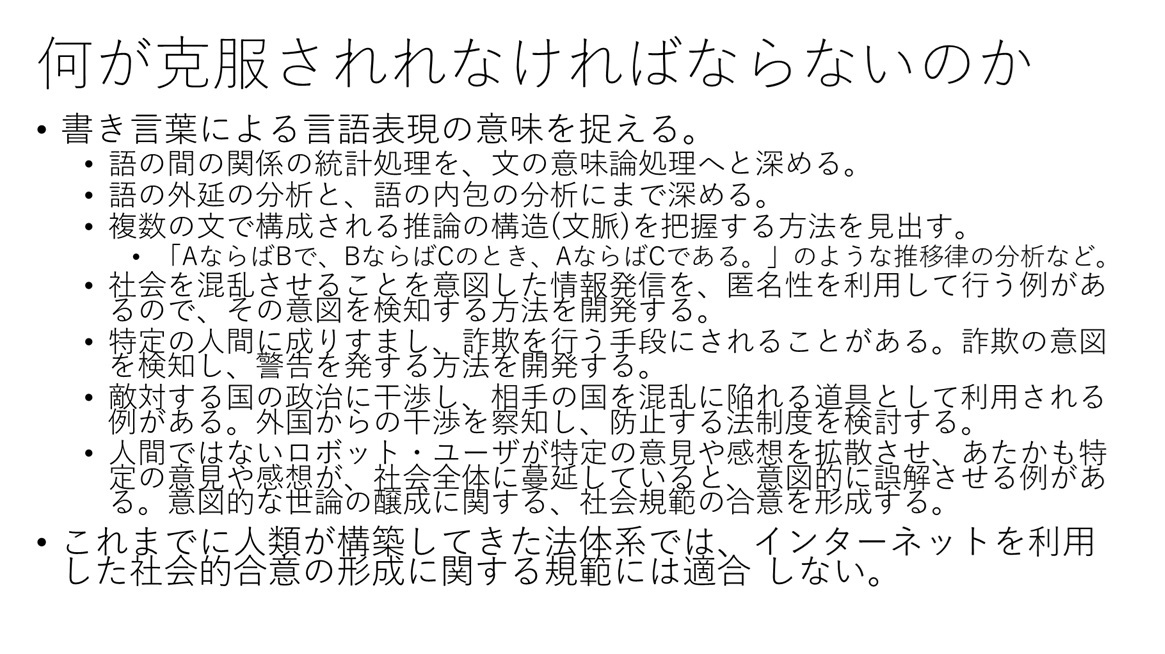
図16. 何が問題か
さらに、ソーシャル・ネットワーク・サービスでは、個々のユーザが過去に閲覧した、他人の投稿を分析して、そのユーザの興味のありそうな話題を、その閲覧時に指定した検索を頼りに、キーワードから多くの人が連想する文章を、ネッワーク上の記事から探し出し、そのユーザに対して、記事の閲覧を推薦するようになっています。これは、単純に検索キーワードの照合だけにとどまらず、過去に閲覧した記事の内容を、人工知能の機能を応用して分析し、どの記事を推薦すべきかを決定するようになっています。つまり、その人が興味を持つと考えられる記事は、インターネット上のサーバで検索して、ユーザのスマートフォンの画面に、自動的に表示します。このことによって、特定のユーザに限定すれば、その人に配信される記事は、その人の興味がある内容を含むものが中心になります。
このような、情報配信のサービスにおける個人化サービスは、機械学習の技術を利用することで、より精度を高め、より顧客にとって満足がゆくように、改善が続けられています。逆に言えば、特定のユーザが、過去に興味を示さなかった問題や内容に関する記事は、そのユーザのスマートフォンでは、あたかもネッワーク上には存在していないかのように見えるわけです。この「情報推薦」の個人化は、ソーシャル・ネットワーク・サービスの運営が、私企業で実施されており、そのサービスの運用に必要な諸費用を、スポンサーからの広告収入に頼っていることから、ユーザの閲覧数を増加させることが、そのサービスを提供している企業にとっては、利潤を極大化するために重要な問題だからです。
さらに、特定の情報(記事)をネットワーク上に公開しているユーザにとっても、数多くのユーザに閲覧される記事については、サービスを提供している事業者から、広告収入の一部が、記事の提供者に支払われる契約になっており、この広告収入を、生活のための重要な収入源にしている人々も少なくありません。このような事情もあるため、個々の記事を公開するユーザは、その内容に対して、なるべく多くの、不特定多数の人々の興味を集められるように、中身の表現を編集するようになっています。この「読者の数を増やそうとする」意図から、記事の内容は、その表現の正確さよりも、その表現が「人々の興味を捉えられるかどうか」が重要になります。このことが、しばしば、ソーシャル・ネットワーク・サービスで提供される情報の正確性や内容の表現が適切ではない事例が、散見される原因になっています。
ソーシャル・ネットワーク・サービスで提供される情報の真偽については、特に、その「内容に誤りがある」情報について、その正しさの検証が問題にされています。この「正しさの検証」も、機械学習などの人工知能技術を応用することで、コンピュータを利用して実行することは可能です。しかし、そのような「正しさの検証」を行い、公開される「情報の正しさ」の質を向上させることは、社会的には意味があっても、ソーシャル・ネットワーク・サービスを運営する事業者にとっては、大多数のユーザの目から見た、「記事の魅力」をそぎ落とし、広告収入を減らすようにしか作用しません。また、コンピュータを稼働させて、そのような記事の内容を正確にするための処理をするため、より多くのコンピュータを導入し、より多くの電力を消費しなければなりません。それは、私企業の「利益追求の原則」から見ても、記事の「正しさの検証」が、事業者にとっては、それに積極的に取り組む必然性が認められないのです。
このため、ソーシャル・ネットワーク・サービス事業においては、ユーザによって提供される個々の記事の「正しさの検証」は、国家などの公的な機関による統制や監視がなければ、有効な対策が取られることはありません。特に、国家などの公的な機関による統制は、ソーシャル・ネットワーク・サービスを経由して流布された情報が、個人のプライパシーを犯した場合、その個人の社会的な活動に支障を生じる場合、その個人の私的な財産の維持に支障を与える場合、そして、その個人の名誉を著しく傷つける場合などを除き、公的な秩序の維持のために、過剰に権力を行使することは、公的な組織にとって、容易ではありません。むしろ、情報提供者の自由な権利を拘束すると言う理由で、逆に法的な問題を引き起こす可能性もあります。
すでに議論したように、コンピュータによる自然言語表現の解析技術は、現時点では、それほど高い水準にはありません。特に、自然言語の意味を確定するための、文脈の解析、「言葉の内包」の意味の把握などについては、研究の進展が遅く、効率的な解析のコンピュータ化を実現するには至っていません。それでも、一般的な場面での自然言語表現の理解と、自然言語でのコンピュータの応答などについては、大きな問題を発生させずに、簡便な方法を使うことで、十分利用することは可能になっています。これは、言葉を話し始めた子供が、その内容を深く考えていなくても、一見、「つじつまの合う」やり取りをすることができることと、似ているからです。