機械学習系を活用した社会的合意形成の可能性
提供: 有限会社 工房 知の匠
文責: 技術顧問 大場 充
更新: 2025年8月30日
ソーシャル・ネットワーク・サービスの登場によって、人類の情報交換や、知の共有、さらには世論の醸成など、社会生活の様々な局面で、個人の意見や意志を、社会の意思決定に反映することが可能になりました。その反面、ソーシャル・ネットワーク・サービスは、サービスを提供する主体が、利潤の追求を使命とする私企業てあるため、社会にとっては重要な情報の真偽よりも、個々の情報についての閲覧数を極大化することに注目が集まっています。
ここでは、機械学習技術などを応用した、人工知能の能力を活用し、人間と人間が相互に意見を交換して、合意できない論点を明確にし、その合意ができていない命題にどのように対処すればよいかを、人間同士だけの力だけでなく、広い意味でのコンピュータを利用して、お互いに譲歩できる範囲で、互いに歩み寄り、合意を形成する過程と、具体的な技術の可能性について考察します。すでに述べたように、コンピュータを利用することができるようになって、個々の人間が、自由にそして安いコストで、即時に意見を表明することが、できるようになりました。しかし、ソーシャル・ネットワーク・サービスでは、それを利益追求の手段としているため、ネットワークを利用している個々人について、それぞれの人の興味や考え方の傾向を分析し、それぞれの人が求めていると予想できる記事を配信して、できるだけ総閲覧数を増加させようとしています。
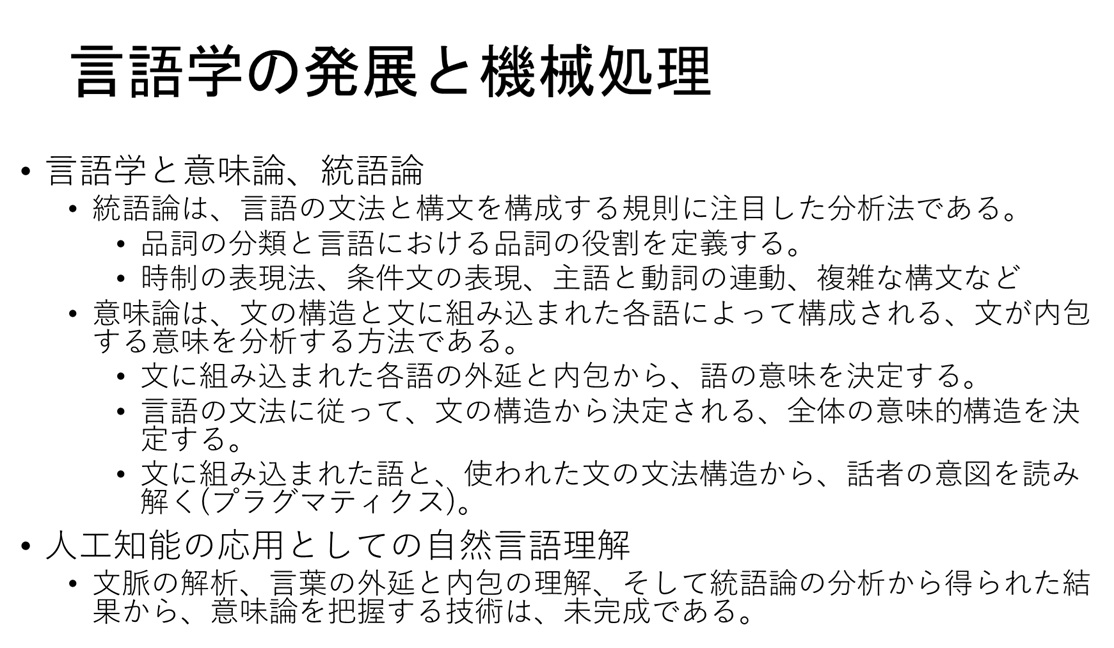
図17. 言語学の発展と機械処理
そのようなソーシャル・ネットワーク・サービス事業が持つ本質的な性質のため、それを利用している人々も、個人の意見や情報を発信しようとするとき、より多くの人々の注目を集め、より多くの人々から賛同を得られる内容や、表現を使って、情報を提供しようと心がけます。このような、ソーシャル・ネットワーク・サービスを提供するサーバに仕組まれた機能と、それを利用する情報発信者の意図とが絡み合って、ソーシャル・ネットワーク・サービスを経由して広められる情報には、(1)表現に誇張が含まれる例がある、(2)内容についてその真偽を確認しにくい情報が含まれる例がある、(3)情報の内容が個人的な見解の表明なのか、観測された事実の報告であるのかの区別が、不明確な場合がある、などの問題が指摘されています。ある個人の意見の表明が、あたかも観測された事実に関する報告であるかのような表現で、ネットワーク上に公開されると、その記事を読んだ人は、誤って、それを事実に関する報告であると誤認する問題も発生します。
2024年にアメリカ合衆国で実施された大統領選挙期間中、大統領候補の一人が、第三者によってソーシャル・ネットワーク・サービスで発信された『証言』を引用し、アメリカ合衆国のある地域にすむ移民の人々が、その地域で飼われていたペットの「犬や猫を食べている」と言う誤情報に基づいて、海外からの移民の中に、アメリカ合衆国の社会では受け入れることのできない問題を起こしている例があるとして、『移民の人々を無条件に受け入れることには問題がある』と、主張しました。この主張は、発言がなされた討論会を管理していた放送局が実施していた「ファクト・チェック」により、事実無根な情報であることが確認されましたが、この主張を信じた一部の市民が、問題にされた地域に居住する、特定の国からの移民の人々を排斥する行動をとった社会的な問題があったと、報告されています。
この米国大統領選挙における「正しくない」情報を、影響力のある個人が公の場で発表し、一部の国民が、その「正しくない」情報を、「正しい」情報であると信じてしまう例は、ソーシャル・ネットワーク・サービスで提供されている情報のごく一部とはいえ、米国大統領候補者で、前大統領の地位にいた人物であると言う事実を考慮すると、その影響力は、決して「小さなもの」であるとは言えません。この選挙の4年前、前大統領は、選挙結果について、自らの「負け」を認めず、「選挙そのものに不正があった」と主張して、『自分が本当の当選者である』と主張し続け、一般の人々に対して、「国会へ抗議のデモ行進をするべきである」と訴え、多数の賛同者が、暴力的な行動に出て、国会議事堂内に乱入し、逮捕されました。この後者の例では、前大統領は、意図的に、国民に対して「選挙の不正があったとの、自分の認識に基づき、選挙結果が正当なものではなく、本来であれば、自分が当選者であった」ことを主張し、人々を扇動しようとした例であると、考えることができます。
これらの例では、ソーシャル・ネットワーク・サービスで提供される情報が、個人の主観的な印象に基づいたものである場合でも、そのことに賛同する人々がいれば、それに賛同する人々にとっては、元になった印象に関する情報が、個人の印象に基づいた情報であっても、「客観的な事実」と「全く同じ」ように伝えられ、その情報を信じる人々が多数であれば、そのことが、それらの人々にとっては、「それこそが真実である」との評価を定着させます。このことは、ソーシャル・ネットワーク・サービスのような情報媒体は、人々の間での情報の共有や、合意の形成を妨げるように、社会を分断化する方向にしか作用しません。そして、人々の間での意見の分断を助長し、合意の形成を困難にします。近年、先進諸国では、政治的な問題における、国民間での極端な意見の分断が顕著になってきています。また、各国における、極右政治勢力の台頭も、これに呼応して増加しています。
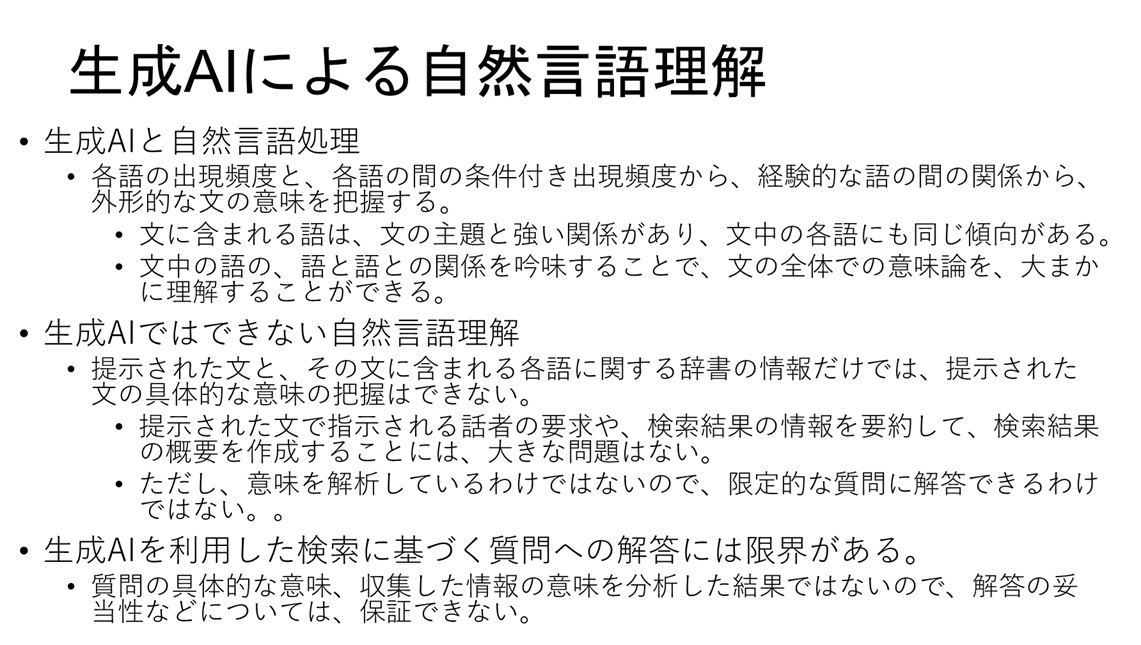
図18. 生成AIによる自然言語理解
アメリカ合衆国では、『反知(識)主義(anti-intellectualism)』と呼ばれる思想が広まっています。これは、自然科学の分野で、新しく獲得された知識を基礎とした人類の知見や、社会科学的な研究で明らかにされた新しい知見に基づいて、人間の行動を変化(進歩)させる、プラグマティズム哲学的な思想を受け入れず、人間の古くからの知的資産(過去の固定観念)に基礎を置いた、中世的な認識に基づいて、人間社会の活動を組み立てるべきであるとする考え方です。例えば、生物の進化における「進化論」の考え方は、聖書の記述に適合しておらず、その考え基づいて、人間社会の知を組み立て、人間の認識の基礎とすることは、「人類の知の進歩を誤った方向性へ導く」として、反対する人々の思想の基礎になっています。
現アメリカ合衆国大統領オフィスの主要メンバーであるバンス副大統領は、そのような『反知主義者』として有名な人の一人だと言われています。バンス氏は、従来は民主党支持者が多かった、オハイオ州の出身で、1990年代から著しく所得を減らした、米国中産階級の出身で、義務教育である高校を卒業した後、軍に入隊し、戦争にも参加しました。軍でのサービスを終えた後、政府が提供した大学への進学応援政策に応募して、有名大学の一つへ進学しました。しかし、大学での勉学に馴染めず、有名大学を卒業した米国社会のエリート層に対する反感を持ち始めたと言われています。彼の『反知主義』の根源は、その時の大学での個人的な認識と、オハイオ州のような保守的な社会で若い時代を過ごし、幼児教育を含めて、基礎知識や規律に関する教育を受けたことと関係があるようです。
バンス副大統領に代表される、反知主義者の人々は、米国社会のエリート層以外の人々の間では、少しずつ増加し続けていると言われています。特に、没落した「貧しい白人」({『ヒルビリー』と呼ばれています)の中産階級の間では、反知主義思想は、確実に増加しつつあるようです。それは、かつて米国社会で裕福な中産階級に属していた白人階層が、アメリカ合衆国の経済発展と伴に、豊かさを享受していたにも拘わらず、社会の変化に伴って、エリート層が豊かになったのに反して、労働者階級に属する人々は、貧しくなっていったからです。このエリート層の繁栄と、労働者層の没落を対比させ、エリート層の富の蓄積の根源である、『知性の差が、貧富の差を生み出している』と、主張するようになりました。富の源泉となる知性を得るためには、高等教育を受けなければなりません。教育を受けるためには、豊かでなければなりません。つまり、現在の米国社会では、豊かでない人々は、ずっと豊かにはなれないのです。
このような社会の構造的な問題によって生み出されている、人々の間の貧富の差を解消するためには、それを形作っている、「知の階層」を破壊するしかない、と考えるのが、反知主義の思想です。そのために、高度な知を生み出している大学の研究機関や、そこで研究に従事する人材を生み出す教育機関に与えられている特権を取り除くべきであると主張しています。しかし、この反知主義の思想は、人間社会における富の配分と、個人における富の獲得競争に大きな影響を与える高等教育の問題(大学教育への入学選抜問題)に、問題を矮小化(わいしょうか)しています。社会の問題しては、社会における所得の配分と、貧困政策、そして教育機会の均等化に、偏りがあることが、本当の問題です。この例のように、社会的な問題の根底には、現象として私たちが認識できる水準の問題と、その問題を生み出している、社会の構造に組み込まれている問題が絡み合っている例が少なくありません。そのような、複雑に絡み合った問題の構造を、解きほぐして、議論を正しい方向へ導く道を示すことは、現在の人工知能では、不可能でしょう。
反知主義と、18世紀から20世紀までの産業革命から産業化社会(Industrial Society)が確立した時代の、経験主義からプラグマティズムの時代の、「正しい知識こそが人類の進歩を約束する」と考える思想は、極端に対立する考え方であり、議論によって形式的に合意を形成することができる問題ではありません。個人個人が、「何を信じているか」と言うような、主体的な信念が問題なのです。このような主体的な信念は、それぞれの立場からの主張を戦わせ、議論を深めても、互いの意見の問題点を修正して、合意を形成する弁証法的なやり方を、表面的に応用することが難しい問題です。そのような理由から、ソーシャル・ネットワーク・サービスなどで交わされる意見は、相互に相手を非難し、敵対する考えの問題点を指摘するだけの、表面的な議論になりがちです。これは、プラトンの「イデア論」と、アリストテレスの「中庸」の議論の、「どちらが人間の思考方法として優れているか」を議論するのと、似たような問題です。合意を形成することは、容易にはできません。どちらが正しいかと言う問題ではないのです。
ソーシャル・ネットワーク・サービスに、機械学習などのコンビュータを活用した知的なサービスを付加して、対立する2つの意見に対して、弁証法を適用して、対立する2つの意見のどちらにも偏らない、新しい考えを生成し、相互のグループに、それを提示して、相互の意見交換を促して、議論をより深いレベルで、新しい局面に導くような機能を実現する新技術の開発が重要になるでしょう。そのような革新的な技術を、現実的に実現できるかどうかは、今の時点で予測することはできません。ただ、人工知能の研究や、機械学習の研究が進み、生成AIを超える新技術が開発できれば、全ての人々が、議論に積極的に参画して、そのような、人間達の間にある意見の対立を解消し、人間社会における、『直接民主主義による社会的な合意の形成』を可能とする新しい人工知能を作り出すこともできるでしょう。